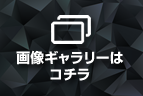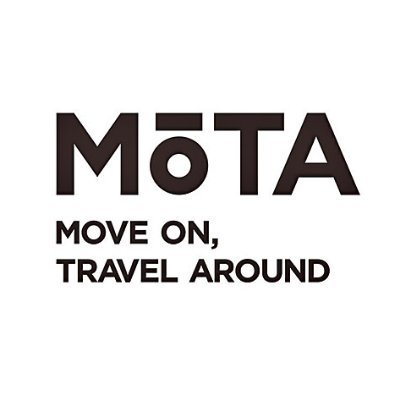ダウンサイジングターボとは|燃費面でのメリット、ターボエンジン車やハイブリッドカーとの違いを徹底解説
ダウンサイジングターボってなに?
エンジンを小型・小排気量化し、ターボでパワーをアップさせるエンジン型式
今や多くの国産車にも採用されているダウンサイジングターボ。その名の通りエンジンの排気量や気筒数を減らし燃料消費を抑える一方、ターボで過給することで、パワーの不足を補うという考え方のエンジンです。そんなダウンサイジングターボについて、メカニズムからその生い立ち、そして今後の展望まで徹底的に解説していきます!
そもそもターボってなに?どんなメカニズム?
エンジンに空気をより多く供給してパワーを上げる装置
ターボは過給機とも呼ばれ、空気をより多くエンジンに供給するための装置です。
ガソリンを多く燃やせば高い出力を得られるということは、何となく想像できると思います。排気量1.5Lの車と3.0Lの車があった場合、パワーがあるのは3.0Lの方という具合です。これは1回の燃焼でガソリンと空気の混合気を1.5L分燃やせるか、3.0L分燃やせるかの違いです。
ガソリンの燃焼には理論空燃比という、過不足なく反応する空気とガソリンの比率(空気:ガソリン=14.7:1)が決まっており、ガソリンを多く燃やすには、その分空気も多く取り入れる必要があります。簡単に言ってしまえば1.5Lより3.0Lの方が2倍ガソリンを燃やせるので、パワーも多く得られるのです。このパワーアップを排気量の拡大以外で実現させるのがターボです。
排気の圧力でタービンを回し、空気を圧縮する
ターボは排気の圧力でタービンを回し空気を圧縮することで、濃い空気をエンジンに送り、通常より濃いガソリンを燃やせるようした装置です。これにより濃いガソリンを燃やすことができ、排気量を変えずにパワーアップさせることができます。
低回転域でターボが十分に効かない“ターボラグ”とその対策
ただターボは排気の圧力でタービンを回すため、低回転域だと排気圧が低いためにタービンが十分回らず、パワーも十分に得られないという課題がありました。
これを解消するために考えられたのが、タービンの小型化や、流入経路の狭小化です。タービンを小型化すれば低い排圧でも十分動作するので、低回転域では小型のタービン、高回転域では大型のタービンと使い分ければ全域でパワーを得られます。これをシーケンシャルツインターボなどと呼びます。また低回転域は狭い排気経路、高回転域は広い排気経路と2系統用意することで、低回転域~高回転域まで十分な過給効果を発揮させるという方法もあります。これをツインスクロールターボなどと呼びます。
またターボ以外にスーパーチャージャーという装置もあります。これはエンジンの回転軸から直接動力を取り出し、コンプレッサーを作動させ圧縮空気を作るというものです。この方法も低回転域から十分な過給ができるため、ターボと組み合わせてツインチャージャーとするシステムも存在します。
普通のターボエンジンとダウンサイジングターボはどう違う?
ターボのメカニズムとしては、普通のターボもダウンサイジングターボも大きく違いはありません。違うのはターボの使い方です。
従来は車を速く走らせるためにターボを採用していました。もともと十分な排気量の自然吸気エンジンを搭載した車両に、さらにパワーを上げた上級モデルとしてターボエンジン仕様車が設定されていたのです。軽自動車にも、同じ660ccの排気量の中でよりパワーをアップさせたターボ搭載車があります。これも考え方としては同じものです。
一方のダウンサイジングターボは、あえて小排気量化し、足りなくなったパワーを補うためにターボを使います。この目的の違いが、普通のターボとダウンサイジングターボの違いです。
ターボエンジンと自然吸気(NA)エンジン
ターボなどの過給器が付いていないエンジンを、自然吸気(NA=Natural Aspiration)エンジンと呼びます。NAエンジンの方が自然な吹け上がりで、より高回転まで回せるため、趣味性の高い大排気量のスポーツカーなどではあえてターボを装着していない車種もあります。
しかしそれ以外、コスト制約の厳しい軽自動車の下位グレードなどを除けば、自然吸気エンジンは今後減っていく可能性があります。
ダウンサイジングターボのメリット
排気量が小さいので燃費アップが期待できる
従来は低回転域で十分な過給効果を出す技術が無く、ある程度回転数を上げなければならなかったため、ターボはモアパワーというニーズに応えるための装置でした。しかし近年はターボラグほとんど無く、低回転域から十分な過給効果を出せる技術が確立されたため、燃費向上の手段としてダウンサイジングターボが採用されています。
排気量が小さくなる分税金、維持費が安くなる
日本の自動車税は排気量の大きさで区分されているため、排気量が小さくなると税金の面でもメリットが生まれます。
例えばホンダ ステップワゴン。ライバルである日産 セレナやトヨタ ヴォクシーが2.0Lのエンジンを積む中、1.5Lのダウンサイジングターボエンジンを採用しています。自家用乗用車の2.0Lでは39,500円ですが、1.5Lになると34,500円となり、年額5,000円の差が生じます。
近年はアッパーミドルクラスの高級車でも、4気筒の2.0Lエンジンを積むのが一般的になってきました。日本の税制だとダウンサイジングはかなりメリットがあるので、積極的に選びたくなりますね。
ダウンサイジングターボとハイブリッドはどう違う?
ダウンサイジングターボはターボ(過給器)で、ハイブリッドはモーターでパワーを補う
考え方としては似ている部分がある、ダウンサイジングターボとハイブリッド。そもそもガソリンのNAエンジンは高回転域で最大出力・最大トルクを発揮するため、低回転域が苦手です。加速の際などはある程度回転数を上げざるを得ませんが、そうすると燃費が悪化してしまいます。
その解決策がダウンサイジングターボとハイブリッドです。ダウンサイジングターボでは低回転域から過給することで、あまり回転数を上げずにパワーを得ることができます。
一方、ハイブリッドの電気モーターも低回転域から最大パワーを発揮するという特性がある為、ガソリンエンジンの苦手な低回転域をアシストする効果があります。解決のアプローチが違うだけで、NAエンジンの苦手な低回転域を補い燃費を向上させるという考え方は同一です。
ストップ&ゴーの多い市街地ではハイブリッドの方が燃費面で有利
ストップ&ゴーの多い市街地では、ハイブリッドの特性が光ります。
現在主流のハイブリッドは、低速域ではエンジンを始動せずにモーターのみで走行ができるようになっています。速度域の低い場合ではエンジンを始動する必要が無くなるため、大幅に燃費を向上させることができるのです。
一方のダウンサイジングターボは、高速道路や郊外などの比較的高い速度域で、長時間走行するような乗り方が得意です。ハイギアード化によって低回転で高速巡行ができるようになっており、その低回転域からでも過給でパワーが出ているために高いドライバビリティが確保されています。
あくまでエンジンなので、モーター加速が苦手な人にも受け入れられやすい
ダウンサイジングターボはあくまでもエンジン自体の低燃費化技術であるため、多くの人が違和感無く運転出来るというメリットもあります。一方のハイブリッドはモーター、モーター+エンジン、エンジンと3つの走行を適宜切り替えるのが一般的です。どうしても従来のガソリンエンジンのみのフィーリングとは異なるため、一部に苦手な人がいるのも事実です。
ダウンサイジングターボとハイブリッドの両立はできない?
ここまで紹介してきたハイブリッドとダウンサイジングターボ、両方採用すればもっと燃費が良くなるのでは?と考えてしまいがちです。
実はメルセデス・ベンツ Sクラスが、直列6気筒ダウンサイジングターボエンジン+ハイブリッドというパワートレインを採用しています。しかし一般的にはほとんど普及していません。なぜならコストの割にメリットが薄いからです。
両方ともNAエンジンが苦手とする低回転域を補完する技術であり、同時に採用しても、燃費改善効果に対するコストアップが見合わないという課題があります。この組み合わせが即座に大衆車へと広がることは無さそうです。
【関連記事】
■メルセデス・ベンツ S450試乗│新世代エンジンとなって復活した“直6”にエンジンの未来を感じた!
ダウンサイジングターボとハイブリッドを両方揃える車種は多い
国産車でもダウンサイジングターボとハイブリッド、両方のパワートレインを用意する車種が増えました。レクサス RX、日産 スカイライン、トヨタ クラウンアスリートなどです。ハイブリッドとダウンサイジングターボは得意なステージが違うので、両方を用意することでユーザーは使用目的に合ったパワートレインを選択できます。
またダウンサイジングターボを採用することで、ハイブリッドの走りを苦手とする層への配慮や走りのイメージアップを図りつつ、ハイブリッドをより上級に位置づけたいというメーカーの思惑もあるようです。
代表的なダウンサイジングターボエンジン採用車
ダウンサイジングターボ採用車は輸入車に多かったが、最近は国産車でも増加
ダウンサイジングターボは欧州車が採用を拡大してきた技術ですが、スバル レヴォーグを発端に、近年ようやく国産車でも採用が増えてきました。またトヨタ オーリスのように、日本国内だけでなく世界市場での販売を意図した世界戦略車にも、ダウンサイジングターボ車両が含まれる例も増えています。代表的な車種を見ていきましょう。
フォルクスワーゲン ゴルフ
ダウンサイジングコンセプトを最初に取り入れたのが、フォルクスワーゲン ゴルフです。
排気量2.0Lエンジンの代替として、1.4Lダウンサイジングターボエンジンが用意されました。TSIエンジンと呼ばれるこのユニットは、2006年のゴルフV途中から導入されています。
フォルクスワーゲン ゴルフはCセグメントのハッチバックでありながら、上級車並の高いボディ剛性と充実の装備で高い人気を博しており、現行型は7代目へと進化しています。この7代目も既にモデル末期で、8代目が登場間近と言われています。
ゴルフVIIIは排気量が1.2L / 1.5Lの新世代ユニットが採用される見込みで、どんな走りを披露するのか、世界から注目が集まっています。
【関連記事】
■2018年夏国内導入の新型ポロGTIとUP!GTI、VWのGTIシリーズをスペインでイッキ乗り!
【関連サービス】
フィアット 500
アニメ『ルパン三世』の作中に登場する車としても知られているのが、この“チンクエチェント”ことフィアット 500です。このフィアット 500にも、ツインエアと呼ばれるダウンサイジングターボエンジンが搭載されています。このエンジンが画期的だったのは排気量を減らすだけで無く、気筒数を2気筒まで減らしたことです。従来の1.4L 4気筒エンジンの代替として、0.9L 2気筒ダウンサイジングターボエンジンが搭載されています。このエンジンは2011年インターナショナルエンジンオブザイヤーとグリーンエンジンオブザイヤーの二冠を獲得しており、環境性能と動力性能、そして2気筒特有の小気味良い回転フィーリングが高く評価されています。
【関連記事】
■FIAT 500 Twinair Sport & Sport Plus 試乗レポート
【関連サービス】
トヨタ クラウンアスリート
▲左:現行型クラウンアスリート / 右:新型クラウン コンセプト
国産勢ではトヨタ クラウンアスリートにもダウンサイジングターボエンジンが採用されています。クラウンアスリートのパワーユニットはとても豊富で、4気筒2.0Lのダウンサイジングターボを始め、V型6気筒2.5L NA、4気筒2.5Lハイブリッド、V型6気筒3.5L NAまで用意されています。このダウンサイジングターボモデルはアスリートのみに設定されており、走りのイメージを訴求するのに一役買っています。現行型クラウンもモデル末期となっており、間もなく次期型が発表される見込みです。
次期型ではアスリート、ロイヤル、マジェスタという名称の廃止や、ガソリンエンジンは全て4気筒ターボに統一されるという噂も出ています。こちらも動向に注目です。
【関連記事】
■トヨタ 新型クラウンが2018年夏に発売!フルモデルチェンジでトヨタFR車初のTNGAを搭載しデザインも一新!|最新情報
【関連サービス】
ダウンサイジングターボに欠点はある?
ダウンサイジングターボは日本の道路事情だと思ったより燃費が伸びないって本当?
ダウンサイジングターボは、ストップ&ゴーの多い日本の市街地だとあまり燃費が伸びないと言われています。
あくまでエンジン自体の効率を改善するユニットであるため、エンジン自体の使用頻度を下げるハイブリッドと比べると、燃費の上昇率は高くありません。
またメーカーカタログに掲示されている燃費はJC08モードで測定されていますが、実際に走行すると、このカタログデータとの乖離が大きくなりがちという指摘もあります。
ダウンサイジングターボエンジンはエンジンオイルの管理がシビア?
ダウンサイジングターボは煤(すす)が発生し易く、通常のエンジンよりもオイル交換をシビアに行う必要があると言われています。これは直噴エンジンであることに起因しています。
ダウンサイジングサーボエンジンと相性の良い燃料直接噴射方式(直噴)
通常のポート噴射エンジンは、混合気(燃料と空気が混ざった気体)の吸入→圧縮→燃焼→排気という予混合燃焼をしていますが、直噴エンジンでは空気のみを燃焼室内に吸入させ、後から燃料を霧状に直接噴射し混合気を作ります。なぜ後から噴射するのかと言うと、圧縮比を高めるためです。
圧縮比とは燃焼室内で混合気が圧縮される比率を表したもので、圧縮比が高いほど熱効率は良くなり、高出力・高トルク、低燃費のエンジンにすることができます。しかし単に圧縮比を高めすぎると、異常燃焼が起きて最悪はエンジンが壊れてしまいます。この異常燃焼はノッキングと呼ばれるもので、混合気の高圧化に伴う温度上昇によって、燃焼室内で不測の発火が起こる現象のことです。
直噴の場合、そもそも圧縮過程が空気だけであれば発火の心配はありませんし、更に燃料噴射の気化潜熱で混合気自体の温度も下がるので、この段階でもノッキングが発生し難くなります。
ターボでは既に圧縮された混合気を燃焼室内に吸入させるため、燃焼室内の圧縮比を上げるのがNAエンジン以上に困難でした。その点、直噴にすれば更に圧縮比を高められるので、直噴エンジンとターボは相性が良いのです。
メーカー指定のオイル交換サイクルを守っていれば問題なし
話が逸れましたが、この直噴エンジンは燃料と空気が混ざる時間が短く、均質な混合気が作り難いために、煤が発生し易いというデメリットがあります。この煤がエンジンオイルを黒くさせるため、オイルを早期に交換した方が良いと言われているのです。
実際は使用状況やエンジン自体の設計(煤が発生しないように条件によってポート噴射も併用しているエンジンもある)にも因るので何とも言えませんが、最低限メーカー指定の交換時期は守った方が良いでしょう。オイル性能やエンジン技術は進化しているので、ある意味耐久性自体は向上しているとも言えそうです。
ダウンサイジングターボエンジンは比較的寿命が短いという説
直噴エンジンは煤が溜まりやすく寿命が短いとの説もありますが、実際は使用状況やメンテナンス状況に因るところが大きく、一概には言うのは難しいところです。そもそも寿命の定義も曖昧で、日本で走行10万kmを超えた車が海外に輸出され、現地で調子良く動いているという事例は多々あります。
私たち一般消費者が本当の意味でエンジンの寿命までその車に乗るということ自体稀かと思いますので、この点はあまり深く考えなくても良いのかもしれません。
記事で紹介した商品を購入した場合、売上の一部が株式会社MOTAに還元されることがあります。
商品価格に変動がある場合、または登録ミスなどの理由により情報が異なる場合があります。最新の価格や商品詳細などについては、各ECサイトや販売店、メーカーサイトなどでご確認ください。
この記事の画像ギャラリーはこちら
すべての画像を見る >愛車の売却を、もっと楽に!もっと高く!
-
一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?
これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。
-
一括査定は本当に高く売れるの?
これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。