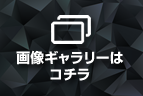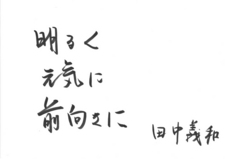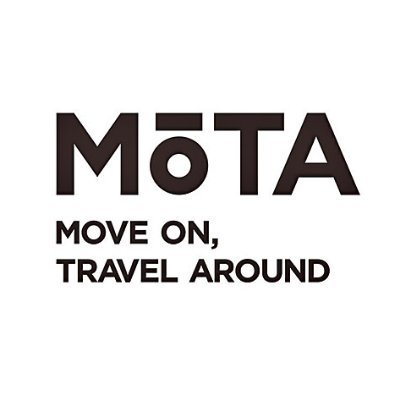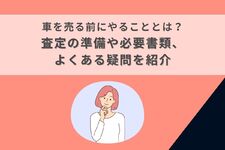THE NEXTALK ~次の世界へ~ トヨタ自動車 田中義和 チーフエンジニアインタビュー(2/5)
- 筆者: 御堀 直嗣
- カメラマン:佐藤靖彦
理詰めで選んだプラグインハイブリッド
まずはじめは、これだけハイブリッドカーで世界をけん引するトヨタが、なぜ、プラグインハイブリッドカーへ進出を図ったのか?プラグインハイブリッドカーは、ハイブリッドカーの次に来るエコカーなのだろうか?
【田中義和】結果的にプリウスを基にしたプリウスPHVとなるわけですが、我々がプラグインハイブリッドカーを開発する際には、最適な姿を求め、バッテリーの搭載容量、エンジンの種類、ハイブリッドシステムの3点について、改めて、優劣をゼロから検証してみました。
まずバッテリーについては、搭載容量を増やすほど電気自動車としてのモーター走行距離を長く伸ばせますが、当然、車両重量は重くなるし、大きなバッテリーを載せるために客室や荷室の広さに制約を受けます。たとえばGMのボルト(レンジエクステンダーと位置付けられる:筆者注)は4人乗りですが、プリウスPHVは5人乗りで、荷室の床も制約を受けません。また自動車メーカーにとっては、バッテリー容量を大きくすると、その分コストが上がるという点も考慮しなければなりません。
次にエンジンですが、排気量など動力性能を吟味する際に留意しなければならないのは、モーター走行でもハイブリッド走行でも、どちらの走行状態でも同じ性能でなければならないということです。たとえば、レンジエクステンダーのようなモーター走行を主に走り、バッテリーの電気が少なくなったら小さな排気量のエンジンで発電する方法をとると、通常運転ではそれほど支障はないでしょうが、坂道を登るというような場合にエンジン騒音が大きくなったり、燃費が悪化したりすることが考えられます。ですから、適切な排気量のエンジンを使うことが大切です。
ハイブリッドシステムについては、モーター走行を主とするシリーズ方式の場合、エンジンで発電した電気を一旦バッテリーに溜め、その後バッテリーからモーターへ電気を伝えるという二度手間が掛かるので、効率が悪くなります。
こうして各項目を検証した結果、プリウスのハイブリッドシステムを活用したプラグインハイブリッド化が適切な開発方向だろうという結論になりました。
「実は…」と田中義和は、トヨタ社内で別の意見もあったと語ってくれている。「社内でも、バッテリー容量を増やし、小さなエンジンでという意見もありました。しかし、検証結果を基に理解してもらいました」と話すのである。
そして、ここで行われたゼロベースでの検証という手法は、そもそも1997年に登場する初代プリウスを開発する際にも、数あるハイブリッド方式からどの方法を選択するかといった際、THE NEXTALK第1回に登場した小木曽聡らが採ったやり方であった。トヨタは常に技術ありきで愚直に検証し、最適な回答を得る努力を惜しまない。
愛車の売却を、もっと楽に!もっと高く!
-
一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?
これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。
-
一括査定は本当に高く売れるの?
これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。