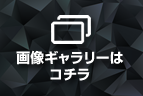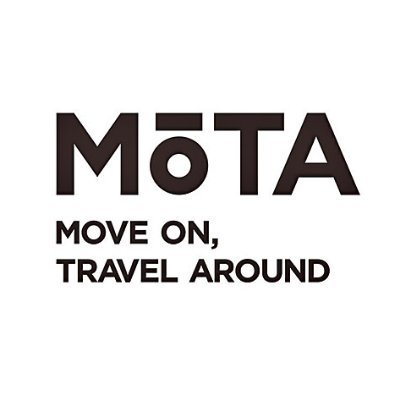マツダの新型CX-8はミニバン層へ受け入れられるのか? 国内最上級SUVの可能性
- 筆者: 渡辺 陽一郎
マツダ 新型CX-8(CX8)売れ行き予想
マツダはSKYACTIVの新世代商品群を投入してから新型CX-5ですでに二巡目。国内でのミニバン要望に応えるべく、新たな提案として3列シートSUVのCX-8国内導入を発表した。SKYACTIV導入以降、クルマの評価は世界各国でも非常に高いマツダ。新たなチャレンジとともに、ブランド戦略もここ数年変えてきている。そんなマツダをユーザー目線で見てみよう。
CX-8はマツダがすでに公表しているSUVで、3列のシートを備えることが特徴だ。SUVでありながら、ミニバンのマツダプレマシーやビアンテの代替え需要に応えることも想定している。発売は2017年の末と見られ、CX-8の発売と併せて、プレマシーやビアンテは販売を終える可能性が高い。
マツダの発表によるとCX-8の全長は4900mm、全幅は1840mm、全高は1730mmとされ、ホイールベース(前輪と後輪の間隔)は2930mmだ。CX-5に比べると全長は355mm、ホイールベースは230mm長く全幅は等しい。全高は40mm高い。つまり単純にいえばCX-5のロング版となる。
3列のシートを収めることを考えると、全長からホイールベースを差し引いた100mm少々は、リア側のオーバーハングに費やすだろう。それでもボディ全体のプロポーションは、CX-5とさほど変わらない。
問題はプレマシーやビアンテの需要を引き継げるか否かだ。
まずはフロア構造とパッケージング(乗員やメカニズムの配置を含めた広義のデザイン)がSUVだから、空間効率はプレマシーやビアンテよりも低い。ホイールベースが2930mmに達するから、2列目のスライド位置を前方に寄せると3列目にも大人が座れるが、膝の持ち上がる着座姿勢になるだろう。マツダが公表した内装写真を見ても、3列目は座面の位置が高く、床との間隔を可能な限り広げようとしている。そうなれば全高を40mm高めても3列目の頭上は狭まる。
また今のミニバン市場では、スライドドアの装着が必須条件になっている。プレマシーとビアンテは両車ともにスライドドアを装着しているから、そこに魅力を感じていたとすれば、ユーザーを引き継ぐのは難しくなる。シートアレンジもミニバンに比べるとシンプルだ。
こういった点を考えると、CX-8はミニバン感覚のSUVというよりCX-5の上級車種だ。公表された写真では、2列目がセパレートシートで、中央にはセンターコンソールが装着される(乗車定員は6名)。装飾類も多い。実際には2列目がベンチシートの仕様も用意するだろうが、4名でゆったりと乗車して、3列目は畳んで荷物を積むのが本来の使い方だ。
価格も高い。CX-5のボディを伸ばして3列目を加えただけでも20万円前後の上乗せになると想定される。メカニズムや装備がクリーンディーゼルターボのCX-5 XDプロアクティブ(300万2400円/2WD)と同等でもCX-8になると320万円だ。トヨタヴェルファイアのベーシックな2.4X、オデッセイアブソルート2.4Xホンダセンシングなどと同等になる。プレマシー20Sスカイアクティブに比べると約100万円高い。マツダの最上級車種と考えるのが妥当で、人気の動向が注目される。
■評価:良
現在の商品ラインナップの充実度と売れ行き
今のマツダ車は、実質的に開発を終えたミニバンと軽自動車などのOEM車を除くと、すべてスカイアクティブ技術と魂動デザインに基づく。そこにはメリットとデメリットがある。
まずはメリットだが、全車のデザインコンセプトが共通だから、マツダのブランドイメージも訴求しやすい。
プラットフォームはデミオ/CX-3、アテンザ/アクセラ/CX-5、ロードスターの3種類だが、前輪駆動のデミオ系とアテンザ系は設計の考え方や構造が似ている。エンジンも共通化が進み、開発力を集中させて商品力を高めやすい。
改良を加えた時も、すべての車種に短時間で水平展開することが可能だ。ステアリングとエンジン出力を連携させて走りを滑らかにするGベクタリングコントロールは、今ではロードスターとミニバンを除く全車が採用する。
このようにメカニズムやプラットフォームの種類を抑え、共通化を進めると開発に要する時間とコストも抑えられるから、メーカーにとっても合理的だ。
逆にデメリットは、商品に統一性を持たせると、種類が限られることだ。今のスカイアクティブと魂動デザインの考え方を、背の高いミニバンやコンパクトカーに反映させるのは難しい。SUVが限界だから3列シート車もCX-8になった。
トヨタや日産はこのようなクルマ造りをしていないから、86とヴェルファイア、GT-Rとセレナをラインナップに揃えられる。マツダも以前はトヨタや日産的な車両開発をしていたが、生き残りを賭けて統一性を持たせた。自ら選んだ道だ。
また、メルセデス・ベンツやBMWを見れば分かるように、統一性を持たせると上級車種には割高感が生じる。アクセラスポーツとデミオでは車内の広さ、走行性能が異なるが、デザインや雰囲気が似ていてボディのイメージカラーまで同じだ。それで価格差が開くと、価格の安いデミオに買い得感が生じる。ただしCX-3はコンパクトSUVの割に価格が高く、CX-5が売れ筋になった。いずれにしろすべての車種をバランス良く売るのは難しい。
表現を変えると良くも悪くも商品が硬直化しており、今のマツダファンにとっては全車が好みに合うが、嫌いな人は全部NGになる。
従って今後は、スカイアクティブと魂動デザインを貫きながら、微妙なテイストを工夫してバリエーションを持たせ、ユーザーに向けた間口を広げることが大切だ。きわめて困難な課題だが、それをしないと今以上に共感を得ることはできず、ユーザーも増えない。
■評価:良
ユーザーサービスの積極性
今はスカイアクティブ搭載車にマツダスカイプランとして実質年率2.9%の低金利を実施している。この金利は低い部類に入る。ただし車両価格の全額を返済するフルローンの場合、販売会社によって金利が異なるので注意したい。
ほかのメーカーにも当てはまる話だが、今のマツダは生産開始を伴う「発売」よりもかなり前から受注を開始する。現行CX-5では2016年11月に内外装の写真と車両の概要を公開。2016年12月に価格を含めた正確な内容を「発表」。「発売」は2017年2月で、この時点で約1万台の受注を貯めていた。
受注を予め募るとメーカーには都合が良い。売れ筋のグレードやオプション装備が早い段階で分かり、部品の発注などの生産計画を立てやすいからだ。生産開始と同時に納車も始められる。
しかし、ユーザーは試乗をせずに注文して納車を早めるか、納得した上で契約して納車待ちを我慢するか、という選択を迫られる。
特に現行CX-5では先代型からの代替えが39%を占め、ボディサイズやエンジン性能などは先代型を踏襲している。そうなると走行性能、乗り心地、内装の質感などが明らかに進化していれば代替えするが、さほど変わらない場合は先代型を乗り続けるという判断もあるだろう。この見極めには試乗が不可欠だから、早期の受注開始は不親切だった。
ほかのメーカーも含めて、受注を開始する時には、プロトタイプでも良いから試乗できる環境を整えておいて欲しい。特に走りの良さにこだわるクルマでは、契約の前段階として試乗は不可欠だ。
■評価:良
ユーザーから見たマツダの結論
スカイアクティブ技術と魂動デザインに支えられたマツダ車は、以前に比べると動力性能、安定性、乗り心地、内装の質感やシートの座り心地、さらに安全装備まで格段に向上した。
それでも国内販売は登録車(小型/普通車)で見ると、2015年度は対前年比が11%のプラスだったが、2016年度は14.1%のマイナスになった。5ナンバー車がデミオのみという品ぞろえも含めて、もう少し車種のラインナップを充実させて欲しい。
[Text:渡辺陽一郎]
愛車の売却を、もっと楽に!もっと高く!
-
一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?
これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。
-
一括査定は本当に高く売れるの?
これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。