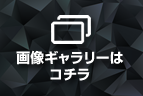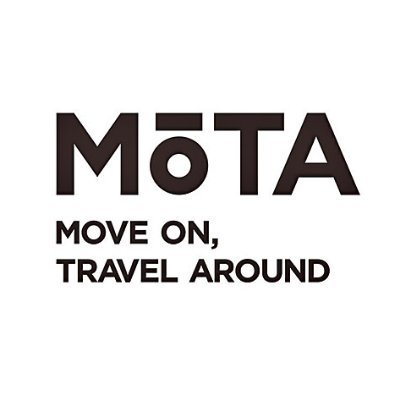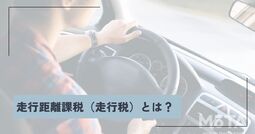“軽自動車の真ん中”ワゴンRに異変? 王道の軽にいったい何が起こっているのか
- 筆者: 桃田 健史
「軽自動車の真ん中」が伸びない
スズキ新型ワゴンRが苦戦している。
一般社団法人全国軽自動車協会連合会によると、2017年3月の同車販売台数は1万3949台で第6位となり、トップのホンダN-BOXの2万6124台の約半分という厳しい状況だ。ワゴンRは6代目として2月に発売開始したばかりだが、一方のN-BOXは今年夏頃にフルモデルチェンジが噂されるモデル末期である。
ワゴンRといえば、1993年のデビュー以来、軽ワゴン市場をけん引し、2016年末時点での累積販売台数は約440万台、このうち約280万台が現時点で保有されているという、軽自動車の王道である。スズキが配布した6代目の広報資料の1ページ目にも「軽自動車の真ん中、それがワゴンR」との記載がある。
その“軽自動車の真ん中”にいま、いったい何が起こっているのか?
市場の成熟と分散化
軽自動車市場が変調している。これが、いまワゴンRの販売に影響を与えている最大の原因だ。
日本国内の全体需要の中で、軽自動車のシェアは“ほぼ半数”に達したが、軽自動車の市場環境自体も成熟してきた。ここ数年は、ワゴンRとダイハツムーヴというツートップを母体として、スペーシアとタントというハイト系に派生、そこにホンダがN-BOXで一気に攻勢をかけるという市場が形成されてきたが、これが崩れ始めている。
そのきっかけを作ったのは、ハスラーだ。同車の購入者の平均年齢は30歳代で、ワゴンRの平均年齢である50代半ばから一気に若返った。これまで軽自動車に興味のなかった層が、ライフスタイル系の新しい乗り物としてハスラーをフックに軽自動車市場に入ってきた。2017年3月のハスラー販売台数は1万240台となり、ワゴンRとの差は少ない。
これは、ハスラーがワゴンRを“食っている”訳ではなく、ハスラーが軽自動車のイメージを変えた、と捉えるべきだ。
また、ワゴンRはクルマとしても成熟した。筆者が6代目を都内の公道で試乗した際、ふと出た言葉が「文句のつけようがないな」である。乗り心地、ハンドリング、車内の静粛性、そしてインテリアの質感や装備品など、中型ミニバンと同等のハイクオリティに達している。
ふた昔前の軽自動車と比べると、雲泥の差である。
とはいえ、5代目からすぐに買い替える人がどれほどいるのかは疑問だ。なぜならば、5代目でも十分にハイクオリティであり、経年劣化も少ないために、買い替えの動機付けが弱いのではないだろうか。
アップサイジングが起こっている?
もうひとつ気になるトレンドが、軽自動車からより大きなクルマへ買い替える、アップサイジングだ。 最近、日本国内各地を巡ると「軽をやめて、5ナンバーにした」という声をちらほら聞くようになった。
地方で景気が良い、ということではないだろうが、ここ数年の日本は政治や経済で大きな変調がなく、全国的にホンワカムードが漂っている。直近では、各地のお花見の現場に行ってみると、社会全体が落ち着いているような雰囲気を感じる。
そうした中、日産ノートe-POWERや、トヨタC-HRなどの販売が好調というトレンドが生まれているが、この中には軽自動車からのアップサイジングの流れも含まれているように思う。さらに踏み込んで考えてみると、いったんは軽自動車へダウンサイジングした人がアップサイジングに転じる、“Uターン需要”もあるのではないだろうか。
この他、もっと大きなトレンドの括りで見ると「所有から共有」という巨大な波も関係してくるはずだ。地方都市では未だに、家族でひとり1台が常識化してきたクルマ社会が存続している。
一方で、都市圏周辺の住宅地などでは、普通乗用車から軽自動車へダウンサイジングした人が「軽自動車すら、もう要らない。必要な時はレンタカーやカーシェアで十分」という意識が高まってきたのではないだろうか。
そうしたカーライフの転換期において、“軽自動車の真ん中”であるワゴンRに対する直接的な影響が及んでいるように思えてならない。
以上のように、ワゴンRを巡る問題には、様々な社会背景が関与しているに違いない。
[Text:桃田健史]
愛車の売却を、もっと楽に!もっと高く!
-
一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?
これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。
-
一括査定は本当に高く売れるの?
これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。