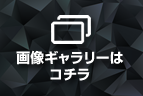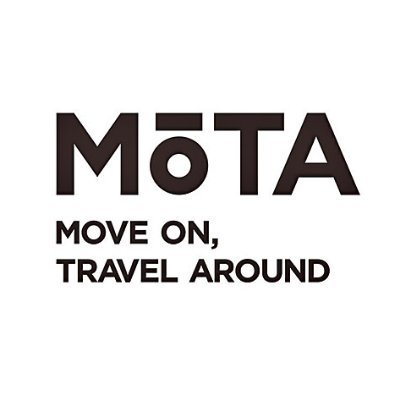エコカーの真相/第一回「災害時のエコカー」(1/2)
- 筆者: 桃田 健史
- カメラマン:桃田健史
ガソリンや灯油などの「燃料不足」で関東全域が混乱
ガソリンがない。灯油がない。
東北地方太平洋沖地震の後、関東全域が燃料不足により大混乱となった。被災地での救援や避難所への物資の配送など、車での移動が困難になる場合も多かった。
東京周辺では、ガソリンスタンドに長蛇の列。
東京湾沿岸の石油コンビナートが生産を中断、千葉の製油所では火災が発生し、関東周辺の高速道路の通行止めなども影響した。
さらには、「もしかすると、東京にも避難勧告が出るかもしれない・・・」という不安感から、ガソリンだけでなく、灯油や食料品の買占めが起こった。
全てが想定外だった。それほど、東北地方太平洋沖地震の規模は大きかった。そうしたなかで、車は無力だった。道路が壊れ、燃料が無く、走ることが出来なかった。
ならば、電気自動車はどうだったか?被災地では当然、停電した。だから電気自動車も無力である。
しかし自治体の中には、ガソリン不足により電気自動車に頼るところもあった。
3月19日、福島県の災害対策本部は地元の日産ディーラーから、電気自動車「リーフ」7台の貸与を受けた。県職員などの移動用として活用。
この他、三菱「i-MiEV」の使用も行うとした。
だがこの場合、航続距離に関する「本当のこと」を、自動車メーカー側が各自治体へ包み隠さず「全てを話す」必要がある。
ヒーターの使用や走行速度によって、カタログへ記載されている航続距離「160km」は、100km以下、80km以下、さらにはそれ以下に激減する場合がある。使用方法による航続距離の大幅な変化について、本来は自動車メーカー側がユーザーに対し、詳細に説明する必要があるはずだ。
だが、「リーフ」の開発担当者によると、公正取引委員会から「ある一部の民間企業が自社の独自判断で(航続距離の変化を)周知することは出来ない」旨の通知を受けた、という。
そうしたことから、結果的に「リーフ」「i-MiEV」とも、航続距離に対して「玉虫色の解釈」のまま市販されている。
だが、被災地の自治体にとって、航続距離の解釈は重大な課題だ。決められたルートを巡回するだけでなく、不測の事態にも臨機応変に対応する場合も出てくる。
その際、想定内の航続距離が稼げなければ、立ち往生してしまう。
被災地周辺では、急速充電の対応にも限界がある。こうした「電気自動車の真相」を、被災地の自治体が自覚した上で、あくまでも「その場しのぎ」の代替車として、電気自動車を使って頂きたい。
愛車の売却を、もっと楽に!もっと高く!
-
一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?
これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。
-
一括査定は本当に高く売れるの?
これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。