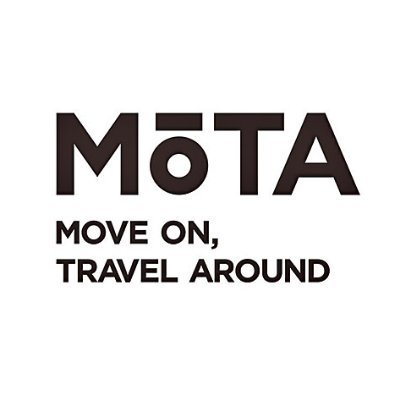デイライトの取り付け方を徹底解説
- 筆者:
おすすめ関連記事・コンテンツ
デイライトとは何か
「デイライト? どんなライト?」と思う方も多いでしょう。デイライトとは簡単に言えば昼間専用のライトのこと。対向する車がお互いに遠くからでも認識しやすくなるように、ヨーロッパや北米で普及が進む灯火類です。日本ではあまり一般的ではなく、少し前まではデイライト装備は車検に通らないこともありましたが、現在は法律上認められており、少しずつ普及しはじめました。ちなみに“デイライト”は正式にはDRL(DAYTIMERUNNINGLIGHTSまたはLAMP)、日本語では昼間常時点灯ライトという名称になります。
デイライトは、北欧発祥の実用的な車の装備です。日本でも雨天時など、コンディションの悪い昼間などにヘッドランプを点灯する車両がいますが、交通量も比較的少ない道路でお互いに自車の存在を早くから周囲に知らせる意味から点灯が普及。北欧各国では、70年代後半から義務化されました。90年代に入ると、カナダやアメリカでもデイライトの普及が進みます。カナダでは、現在は装着が義務化、アメリカでは義務化はされていませんが、アメリカ国内で販売される車両すべてにデイライトが装着されるようになりました。
デイライトの特徴
次にデイライトの特徴を挙げてみましょう。ヘッドライトを常時点灯させると、テールランプやメーター照明も点灯してしまいます。デイライトの場合は、テールランプやメーター照明と連動して、点灯しない仕組みとなっています。北米でデイライトが普及し始めたころは、イグニッションをオンにするとデイライトが点灯、任意で消灯することはできませんでした。しかし、市街地では目立ちすぎるとのことで、一部車種では任意にON/OFFが可能なスイッチが設けられています。2011年以降にEUでもデイライトの義務化がスタートしましたが、そのタイミングでデイライトのLED化が進みはじめました。
日本国内では、2016年10月7日に保安基準の改正が行われ、昼間走行灯(デイライトのこと)に関する規定が新設され(300カンデラを超えたものでも自動車に装着することが可能など)、デイライトが事実上、解禁されました。それ以前に日本に輸入された車では、正規輸入モデルではデイライト機能を停止したり、保安基準に違反しないように輝度や点灯面積を加工しポジションランプに変更したりと、日本に合わせた仕様変更が行われていました。保安基準改正前に販売されたデイライトとしての機能が停止された車も、デイライトとしての機能を復活させることができるのではと考えてしまいますが、技術的な対応が可能であっても、保安基準改正前に販売されたものについては、点灯機能の復活は改造行為となるので、法的問題が完全にクリアされたわけではありません。その辺りは正規販売店で確認することをおすすめします。
車検に適合するデイライトの基準
2016年10月7日に行われた“道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】〈第一節〉第124条の2(昼間走行灯)”では、デイライトについて次のように明文化されました。
①光度は1440cd以下であること
②照射光線は他の交通を妨げないもの
③白色であること
④灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと
⑤レンズ取り付け部に緩み、ガタ等がないこと
⑥照明部の大きさは、25平方センチメートル以上200平方センチメートル以下であること
これ以外にも、デイライトの個数(2個)と装着間隔・装着位置、フォグランプ又はヘッドライト点灯時には、デイライトは消灯するようにしなければならないなど、取り付けに関する細かなルールが定められており、これらの要件をクリアしていれば、車検をパスすることができます。もちろん、保安基準改正後にデイライトが装着された新車ならば何も問題視することはありません。
デイライトはヘッドライト点灯時には消灯していなければならない
問題なのは後付け(新車購入後に自力、あるいはカー用品店などで取り付けてもらう場合)のケースです。
保安基準に適合した製品で、取り付位置も保安基準どおりに装着すれば問題ないことから、自分で取り付けを考える人も多いかもしれません。しかし、「フォグランプ又はヘッドランプ点灯時にはデイライトは自動的に消灯するようにしなければならない」という項目がやっかいな問題になってきます。要するに、ヘッドランプとフォグランプ、そしてデイライトを同時に点灯してしまうと、保安基準違反となってしまうのです。「自動的な消灯」となっているので、任意にオン/オフが可能となるスイッチの介在は認められないのが大原則です。このあたりを整備士に尋ねてみると、「自力装着の場合は、ヘッドランプなどとの同時点灯を防ぐ自動消灯機能がないことがほとんどで、保安基準不適合になるケースが多い」と話してくれました。
前章でも少し触れましたが、取り付けでの最大の難所にも見えるのが、フォグランプやヘッドランプとの同時点灯が認められていないことです。しかも、デイライトはフォグランプやヘッドランプの点灯に連動して、「自動的に消灯しなければならない」ことになっています。
デイライト取り付けのパターンその1
デイライトの種類を調べてみると、主に2つのパターンがあります。一つ目は、LEDの側面発光テープを保安基準に適合するサイズに加工して取り付けるDIY度の高い取り付け方法。配線に関しては、いまではエンジンのオン/オフに対応してLEDも自動的にオン/オフとなる専用ハーネス(配線)などが市販されていますので、比較的簡単に作業を行うことができるでしょう。DIY度が高いので、取り付けにかかる費用はかなり押さえることができますが、このケースではフォグランプやヘッドランプ点灯時に自動消灯する機能はこの時点では担保されていません。車検を通るか通らないかはグレーゾーンとなってしまいます。
デイライト取り付けのパターンその2
二つ目は、ポジションランプにデイライト機能を持たせたものに交換する「純正対応タイプ」などと呼ばれるものです。このほかにフォグランプにデイライト機能を持たせているものもあります。この方法ならデイライトとして点灯しているときは計器盤照明及びテールランプが点灯することはないですし、保安基準にある“自動消灯機能”も担保することができます。ポジションランプ一体となるタイプは、フィット感はいいのですが、もともとLEDポジションランプ装着車に設定が限られるのが難点です。
保安基準を満たすデイライトにするには
カスタムパーツに強いディーラーに確認したところ「デイライトは商品の種類も豊富で、装着して保安基準不適合か否かどうなるかを、ユーザーの自己責任に任せる商品もあります。新車ディーラーはコンプライアンスが厳しいため、保安基準に適合する商品を装着します」とのこと。また、市販のデイライトの中には緑色のLEDを採用している製品もありますが、本来保安基準不適合となるのだが、検査官次第ではパスすることがあります。検査場の判断にはバラつきがあるようです。
北米で販売される新車には、すべてといっていいほどデイライトが装着されています。欧州でも義務装着化が2011年からというのを考えれば、加速度的に新車への装着が進んでいるのがわかります。そのような状況下で国産車の対応は後手にまわっており、日本国内でのデイライトの認知が、目立って広がりを見せていないように思われます。
燈火類のLED化の遅れ
その背景にあるのは、灯火類のLED化が国産車は遅れている点でしょう。欧州車だけでなく、アメリカンブランド車、そして中国メーカー車では、ヘッドランプやポジションランプ、ウインカーやリアコンビネーションランプのLED化が加速度的に進んでいます。そのため、ポジションランプにデイライト機能を持たせ、さらにウインカー機能まで持たすモデルも存在しているほどです。しかし、国産車の灯火類のLED化はまだまだで、北米で販売される日本車のなかには、デイライトがいまだに独立した電球タイプのものも目立っているほどです。
国内専売車にはデイライト装着義務がない
二つ目は日本国内市場に目を向けると、国内販売される多くが日本国内専売モデルとなっているということ。デイライトが義務装着とならない日本国内専売車では、デイライトの標準装着はフロント灯火類のレイアウトなどでは想定されていないケースがほとんど。これは欧州や北米に比べれば、デイライトを必要とする走行シーンが日本国内では少なことも影響しています。デイライトのことを改めて調べていくと、日本市場のガラパゴス化が加速していることを、強く感じます。
愛車の売却を、もっと楽に!もっと高く!
-
一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?
これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。
-
一括査定は本当に高く売れるの?
これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。