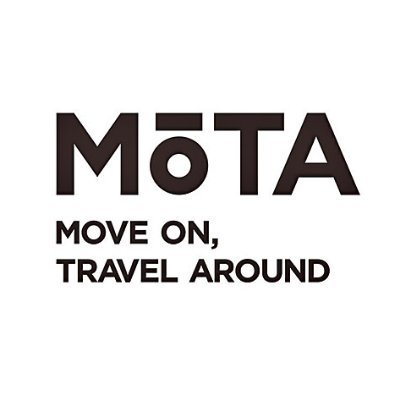インド自動車市場の現状/日下部保雄のコラム
- 筆者: 日下部 保雄
- カメラマン:日下部保雄
インド自動車市場の現状/日下部保雄のコラム
劇的に成長する中国に続いて、同じくアジアで注目されるインドに行ってきた。
中国は凄まじい速度で変わっていくが、インドはそれに比べるとユッタリと経済成長を続けているように見える。しかしGDPに対する工業化率も年々上がっており、この5年間で7%から11.6%に増え、さらに2015年には14.2%と予想される。この数字からするとやはり中国が異常な工業成長率を達成しているといった方が正しいだろう。
国全体がなりふり構わず突進している感じで、自動車で言えば最初は(今でも?)デッドコピーをものともせずに大量のメーカーが乱立し、その結果としてココ2~3年で独自性を打ち出そうとしている。
いくら中国の経済成長が高いといってもこれだけのメーカーが存続できるとは考えられず、次第に淘汰されつつ、パワーのあるところに吸収されていくだろう。
中国には日本では知られていないクルマが山のようにあるが、インドもタタ・ナノ以外に結構知られていないメーカーがある。
トップメーカーはご存知のように「マルチ・スズキ」。型遅れのアルトを販売しているイメージが強いが、スイフトを始め、その他にも13車種ものラインナップを揃えている。
一方、「 タタ・モーターズ」は20万円カーですっかり有名になったナノ以外に、インディカ、インディゴなど9車種を揃える。
民族系では他にアンバサダー(1957年登場!)を作る「 ヒンダスタン・モーターズ」がある。未だに販売されていることが奇跡だが、今ではディーゼルはユーロ4をクリアしているらしい。多目的車ではICML、マヒンドラ、プレミエールなどがあり、いずれも商用車などが中心で、インドのロジスティックスを担っている。
したがって、乗用車はタタとスズキなどの外資系が圧倒的だ。外資系としては、「ヒュンダイ」「VW」「シボレー」「シュコダ」などがメジャープレイヤーだが、ロールスロイスやランボルギーニ、ポルシェも販売されている。
そう言えば、私の行った先の南部の高原都市、バンガロールではタタ傘下のジャガーやランドローバーも見なかった。この街には、F1のフォース・インディアを持つオーナーの大邸宅があったが、そのガレージにはどんなクルマが何台入っているのか、想像すらつかない。
自動車市場におけるインドの潜在需要は
さて、中国では富裕層向けに大きなクルマの需要が先に来て、今は富裕層だけでなく高度成長期の日本のようにコンパクトカーの需要が伸びつつある。(中国はバブルと高度経済成長が一度に押し寄せているようなイメージ)
インドでは国民性だろうか、大きなクルマや高価なクルマは注目されず、商用車など実用性を重視した身近なクルマに人気が集まる。その為、マルチ・スズキが地道な努力によって乗用車の販売を成功に収めたのは、その国民性とニーズをよく理解していたからであろう。
そして、中国に次ぐ11億の人口と日本の10倍の国土が、クルマの必要性をますます広げることは明白だ。ちなみにインドでのクルマの普及率は人口1,000人に対して8台。日本では1,000人に対して400台なので、如何に潜在的な需要が大きいかが分かる。
そして、インドでは人がバイクに群がるように乗っている光景をよく見かける。公共交通機関も、それこそ溢れかえって人が乗っており、そういった意味ではタタのナノは優れた発想で造られたクルマであり、インドのためのクルマであると言えるだろう。
ナノを、安全基準や運動性能など日本・欧州の基準で語ってはいけない。最小限の必要装備でクルマの利便性を満たしていればそれでOKなのだ。
ただし、大ヒットになってきているかといえば、供給の問題もあり必ずしも当初期待したほどではないように見える。すでにクルマの快適性を求める人々からは物足りなさが感じられることと、上級グレードはスズキなどとの価格差が少なくなっていることが要因のようだ。むしろ、タタ・インディゴのようなもう一クラス上のクルマを良く見かけた。
インドの自動車市場は、トヨタが参入を宣言している本年末からいよいよ激しい競争に突入する。各メーカーは前述の潜在需要をいかに掘り起こせるかが、勝負の鍵を握ることになるだろう。
愛車の売却を、もっと楽に!もっと高く!
-
一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?
これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。
-
一括査定は本当に高く売れるの?
これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。